桃の木は庭に植えてはいけないって聞いたことありませんか?
私も最初にこの話を聞いたとき、「えっ、桃って縁起が良いんじゃないの?」って思ったんです。
実際、近所のTさんも桃の木を植えたいって相談されたことがあるんですが、ネットで調べてみると「植えてはダメ!」みたいな情報がたくさん出てきて困惑されていました。
でも安心してください。実際のところ、桃の木を庭に植えることに関するこれらの噂や理由を詳しく調べてみると、そのリスクやデメリットのほとんどは適切な知識と管理で解決できることがわかったんです。
桃の木を庭に植えてはいけないと言われる理由は確かにありますが、正しい育て方を知っていれば全く問題ありません。
まず最初に要点だけをまとめると……
- 病害虫が多く管理に手間がかかるのは事実だが、適切な対策で解決可能
- 大きく育つため剪定は必要だが、鉢植えでコンパクトに育てることもできる
- 風水的な悪影響の噂は迷信であり、むしろ魔除けとして縁起が良い
- 連作障害などの問題も正しい植え方で回避できる
- 一本でも実がなる品種が多く、家庭栽培にも適している
この記事では、私が実際に桃の木を育てている経験や、ご近所さんたちの体験談も交えながら、桃の木に関する悪影響の噂を検証して、正しい育て方をお伝えしていきますよ。
桃の実がなる庭って憧れませんか?春には美しい花を楽しんで、夏には甘い桃を収穫できるなんて、想像しただけでワクワクしますよね。
桃の木を庭に植えてはいけない5つの理由やデメリット
桃の木を植えてはいけないと言われる理由について、よく言われるものを5つピックアップして検証してみました。
実際にこれらの理由を知っておくことで、適切な対策が立てられるようになります。
- 病害虫が多く、管理に手間がかかる
- 大きく早く育つため、庭のスペースを圧迫しやすい
- 根から毒性のある成分を出し、周囲の植物の成長を阻害する
- 風水的に植える方角によって悪影響とされる場合がある
- 果実がなると動物や害虫が寄りつきやすくなる
それでは、これらの理由を一つずつ詳しく見ていきましょう。
理由1:病害虫が多く、管理に手間がかかる
桃の木は確かに他の果樹と比較して病害虫の被害に遭いやすい果樹です。
私の知り合いのMさんも、最初に桃の木を植えたときは「こんなに大変だと思わなかった」って言ってました。でも、今では毎年美味しい桃を収穫されているんです。
主な病害虫とその対策をまとめてみますね。
- 縮葉病:葉が縮れて赤くなる病気。春先の薬剤散布で予防可能
- せん孔細菌病:葉に穴があく病気。風通しを良くして湿度を下げることが重要
- 灰星病:果実が腐る病気。袋かけで予防できる
- アブラムシ:新芽につく害虫。見つけ次第駆除すれば問題なし
- カイガラムシ:枝につく害虫。冬の石灰硫黄合剤で対策可能
確かに管理は必要ですが、年間を通してスケジュールを立てて対策すれば、そんなに難しいことではありません。
近所の園芸店の方に聞いたところ、「桃は手をかけた分だけ応えてくれる果樹」だそうです。定期的な薬剤散布と適切な剪定、そして袋かけを行えば、立派な実を収穫できますよ。
良い実を収穫するためには摘果(実の数を減らす作業)も大切で、一つの枝に実をつけすぎないようにコントロールすることがポイント。
理由2:大きく早く育つため、庭のスペースを圧迫しやすい
桃の木は確かに生長が早く、放任すると樹高が3〜5m、枝張りも3〜4mと大きく広がります。
狭い庭では他の植物の日当たりを遮ったり、隣家への越境問題が起こる可能性があるのは事実です。
私の近所のKさんのお宅でも、最初は小さかった桃の木が数年で大きくなって、お隣さんとの境界線ギリギリまで枝が伸びてしまったことがありました。
でも、この問題は適切な剪定で解決できるんです。
- 冬季剪定:12月〜2月に不要な枝を切り落とす
- 夏季剪定:7月〜8月に徒長枝を整理する
- 樹形管理:Y字型やハート型に仕立てて高さを抑える
- 鉢植え栽培:矮性台木を使った品種なら2m程度に抑えられる
実際、Kさんも適切な剪定を覚えてからは、コンパクトで実つきの良い桃の木を維持されています。
剪定は最初こそ「どこを切ったらいいかわからない」と感じるかもしれませんが、基本を覚えれば意外と簡単。樹形を小さく保ちながら、毎年実を楽しむことができますよ。
鉢植えなら移動もできるし、ベランダでも栽培可能。スペースに制限がある場合は、鉢植え栽培も検討してみてください。
理由3:根から出る成分が周囲の植物の成長を阻害する
桃の木には確かに「忌地現象」と呼ばれる問題があります。
これは、桃の木を植えてあった場所に再度桃を植えるとうまく育たないという現象のことです。
また、根から分泌される物質が他の植物の成長を阻害することもあると言われています。
ただし、この現象は「植物同士の化学的な相互作用によるものです。
対策方法はちゃんとあります。
- 植栽位置の工夫:他の植物から2m以上離して植える
- 土壌改良:植え穴に新しい土を入れる
- 根の処理:前に植えていた桃の根をきれいに取り除く
- 他品種との混植:相性の良い植物と組み合わせる
未成熟な果実や種子にアミグダリンという青酸配糖体が含まれるのは事実ですが、完熟した果実を普通に食べる分には全く問題ありません。
実際、私たちが普段食べている桃は安全そのもの。種を大量に食べるようなことがなければ、心配する必要はありませんよ。
理由4:風水的に植える方角によって悪影響とされる場合がある
風水では、桃の木を植える方角によって運気に影響があるという説があります。
具体的には、こんな迷信が言われることがあるんです。
- 北に植えると男性の女性関係にトラブルが生じる
- 東に植えると足に関する問題が起こる
- 西に植えると貞操観念の揺らぎが生じる
- 南に植えると家全体の運気が下がる
でも、実際のところ桃は古来から「邪鬼を払う力がある」とされる非常に縁起の良い木なんです。
むしろ桃の節句(ひな祭り)でも使われているように、魔除けや厄除けの象徴として親しまれてきました。
私の近所のSさんは風水を気にされる方ですが、「桃は本来縁起の良い木だから、気にしすぎる必要はない」とおっしゃっていました。
実際、Sさんのお宅では南向きの庭に桃の木を植えていますが、何の問題もなく元気に育っています。
風水を参考にするのは自由ですが、科学的根拠はありません。日当たりや風通し、土壌条件といった実際の栽培環境の方がずっと重要ですよ。
どうしても気になる場合は、北東(鬼門)や南東の方角に植えるのが良いとされています。
理由5:果実がなると動物や害虫が寄りつきやすくなる
甘く熟した桃の実は、確かにカラスやハクビシンなどの野生動物を引き寄せやすくなります。
私の知り合いのYさんも、「せっかく大きくなった実をカラスに食べられてしまった」という経験をお持ちです。
また、落ちた実が地面で腐敗して、アリやハエが寄ってくることもあります。
でも、この問題も適切な対策で十分に解決できるんです。
効果的な対策方法をご紹介しますね。
- 袋かけ:実が小さいうちに袋をかけて保護する
- 防鳥ネット:木全体をネットで覆う
- 収穫タイミング:完熟前に収穫して室内で追熟させる
- 清掃管理:落ちた実はすぐに拾って処分する
- 花桃の選択:実を目的としない観賞用品種を選ぶ
Yさんも袋かけを始めてからは、カラスの被害がほとんどなくなったそうです。
袋かけには少し手間がかかりますが、その分きれいで美味しい実が収穫できるんです。
実際、袋かけした桃は色も良く、傷もつかないので見た目も美しく仕上がります。
手間をかけた分だけ、収穫の喜びも大きいですよ。
【結論】気になる点はあるが断念する必要はない!
ここまで桃の木を植えることのデメリットを見てきましたが、結論から言うと、これらの問題は全て適切な知識と管理で解決可能です。
確かに手間はかかりますが、それ以上に得られる楽しみや満足感の方がずっと大きいんです。
- 春の美しい花を楽しめる
- 夏には甘くて美味しい実を収穫できる
- 魔除けや厄除けとしての縁起の良さもある
- 家族で収穫の喜びを共有できる
私も実際に桃の木を育てていますが、春に咲く花の美しさや、収穫期の楽しみは他では得られない特別なものです。
最初は病害虫の管理や剪定に戸惑いましたが、慣れてくると季節ごとの作業が楽しくなってきました。
近所の方々も、最初は「難しそう」と敬遠されていた方が多かったのですが、実際に育ててみると「思っていたより大変じゃなかった」とおっしゃる方がほとんど。
適切な品種選びと基本的な管理方法を押さえれば、初心者の方でも十分に育てることができますよ。
桃の木は庭に植えてはいけない説を否定した正しい育て方
それでは、桃の木を実際に庭で育てるための正しい方法をご紹介していきますね。
基本的な情報から植え付け、日常の管理まで、ステップごとに詳しく解説していきます。
- 桃の木の基本情報を理解する
- 縁起の良さや風水について知る
- 適切な植える方角を選ぶ
- 正しい植え付け方法を実践する
- 鉢植えでの栽培方法を学ぶ
- 剪定のコツを身につける
- 実がなるメカニズムを理解する
- 桃の木の寿命について知る
基本情報(特徴・種類・育てやすさ)
桃の木について、まずは基本的な特徴を理解しておきましょう。
バラ科スモモ属の落葉低木から小高木で、原産地は中国とされています。
日本では古くから栽培されており、春には美しい花を咲かせ、夏には甘い果実を実らせる魅力的な果樹です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 学名 | Prunus persica |
| 分類 | バラ科スモモ属 |
| 樹高 | 3〜5m(剪定により調整可能) |
| 開花期 | 3月〜4月上旬 |
| 収穫期 | 6月〜9月(品種による) |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
桃の品種も豊富で、収穫時期や果実の特徴によって選ぶことができます。
| 品種系統 | 特徴 | 代表品種 |
|---|---|---|
| 白鳳系 | 果肉が柔らかく、果汁が多い | 白鳳、日川白鳳 |
| 白桃系 | 果肉が硬く締まっており、日持ちが良い | あかつき、川中島白桃 |
| 黄桃 | 果肉が黄色く、加工にも適している | 黄金桃 |
| 花桃 | 観賞用で八重咲きなど花が美しい | 源平桃、菊桃 |
| 矮性品種 | コンパクトに育ち、鉢植えに適している | ちよひめ、ひめこなつ |
育てやすさについては、「中程度」というのが正直なところ。
病害虫の管理は必要ですが、適切な手入れをすれば初心者でも十分に育てることができる果樹です。
桃栗三年という言葉があるように、植え付けから3年程度で実がなり始めるのも魅力的。
私の経験では、最初の1年は樹を大きくすることに専念して、2年目から少しずつ実をならせるようにすると、その後の成長が良好になります。
樹勢が強いので、環境が合えば比較的丈夫に育ってくれますよ。
庭に植えるとどんな縁起がいい?魔除けや厄除けになる?
桃の木は実は非常に縁起の良い木として古くから親しまれてきました。
「桃の木は庭に植えてはいけない」という説とは正反対に、桃には強力な魔除けや厄除けの力があるとされているんです。
これは迷信ではなく、日本の古い文献や中国の神話にも記載されている由緒正しい言い伝えなんですよ。
古事記では、イザナギノミコトが黄泉の国から逃げる際に、桃の実を投げて邪鬼を退散させたという記述があります。
このことから、桃には邪悪なものを払う霊力があるとされてきました。
中国でも桃は「仙木」と呼ばれ、不老長寿の象徴として大切にされています。
縁起の良い効果として言い伝えられているものをご紹介しますね。
- 邪気払い:悪いものを寄せ付けない力がある
- 魔除け:災いから家族を守ってくれる
- 長寿祈願:健康で長生きできるよう願いを込められる
- 子孫繁栄:家族の繁栄を願う意味もある
- 厄除け:悪い運気を断ち切る効果があるとされる
実際、桃の節句(ひな祭り)で桃の花が飾られるのも、この魔除けの力を期待してのこと。
女の子の健やかな成長を願って、邪気を払う桃の花を飾るという意味があるんです。
私の近所のHさんも、お孫さんの健康を願って庭に桃の木を植えられました。
「毎年春になると美しい花が咲いて、家族みんなが明るい気持ちになれる」とおっしゃっています。
科学的な根拠はありませんが、美しい花と美味しい実をつける桃の木があることで、確かに家庭が明るくなるのは事実。
そういった意味でも、桃の木は縁起の良い植物だと言えるでしょう。
風水や鬼門を意識した植える方角
風水を気にされる方のために、桃の木を植える適切な方角についてご説明しますね。
基本的に桃は魔除けの力があるとされているので、邪気の入りやすい鬼門に植えるのが良いとされています。
ただし、実際の栽培環境(日当たり、風通し、土壌条件)の方が重要だということも忘れないでください。
- 方角の基本を理解する(家の中心から見た方位を確認)
- 鬼門(北東)の位置を特定する
- 日当たりと風通しを確認する
- 土壌の水はけを調べる
- 近隣への影響を考慮する
- 実際の植栽位置を決定する
風水的に良いとされる方角をまとめると、こんな感じです。
- 北東(鬼門):邪気を払い、家を守護する効果が期待できる
- 南東:成長と家族の幸福を表す方角で桃との相性が良い
- 東:朝日を浴びる方角で生命力を高めるとされる
避けた方が良いとされる方角も一応お伝えしておきますが、あくまで迷信の範囲です。
- 北:男性の女性関係にトラブルが生じるとされる
- 西:家族の貞操観念に影響があるとされる
- 南:家全体の運気が下がるとされる
ただし、これらは科学的根拠のない迷信であり、実際の栽培環境を優先することが大切です。
私が実際に相談を受けた経験では、風水を気にして日当たりの悪い場所に植えて、結果的に樹が弱ってしまったケースもありました。
桃は日当たりを好む植物なので、南向きや東向きの日当たりの良い場所の方が健康に育ちます。
どうしても風水が気になる場合は、北東の鬼門で日当たりが確保できる場所があればベスト。
なければ、実際の栽培環境を優先して、後から風水的な対策(お守りを置くなど)を考えるのが現実的ですよ。
基本的な植え方と育て方
桃の木を庭に植える正しい方法を、ステップごとに詳しくご説明します。
植え付けのタイミングから日常の管理まで、順序立てて実践すれば初心者でも成功できますよ。
- 植え付け時期を選ぶ(11月〜4月が適期、寒冷地は3〜4月がベスト)
- 植える場所を決める(日当たり・風通し・水はけを重視)
- 植穴を掘る(直径・深さともに50cm程度)
- 土壌改良を行う(堆肥や腐葉土を混ぜ込む)
- 苗木を植え付ける(根を広げて浅植えにする)
- 支柱を立てて固定する(風で倒れないよう注意)
- 水やりと追肥を適切に行う(植え付け直後はたっぷりと)
植え付け後の基本的な管理についても、季節ごとのポイントをお伝えしますね。
春(3〜5月)の管理では、新芽の生長とともに病害虫の予防が重要。
芽吹きの時期に縮葉病の予防薬を散布し、アブラムシが発生したらすぐに駆除します。
この時期は水やりも重要で、特に植え付け1年目は乾燥に注意が必要です。
夏(6〜8月)の管理では、実がなっている場合は袋かけを行い、摘果で実の数を調整します。
剪定も軽く行い、風通しを良くすることで病気の予防になります。
水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えますが、与えすぎると実が水っぽくなるので注意が必要です。
秋(9〜11月)の管理では、収穫後のお礼肥を与え、来年に向けて樹勢を回復させることが大切です。
冬(12〜2月)の管理では、本格的な剪定と寒肥を行います。
この時期の作業が翌年の花つきや実つきに大きく影響するので、しっかりと行いましょう。
石灰硫黄合剤を散布してカイガラムシなどの害虫を駆除することも忘れずに。
肥料については、植え付け時の元肥、春の芽出し肥、夏の追肥、秋のお礼肥、冬の寒肥という5回のタイミングで与えるのが基本。
チッ素、リン酸、カリをバランス良く含んだ果樹用の肥料を使うと簡単ですよ。
鉢植えでも育つ?
桃の木は鉢植えでも十分に育てることができます。
庭のスペースが限られている場合や、賃貸住宅でも楽しめるのが鉢植えの魅力。
移動できるので、季節に応じて最適な場所に置けるのも便利ですよね。
- 適切な鉢を選ぶ(直径40cm以上、深さ40cm以上の大きめの鉢)
- 鉢底に排水材を敷く(軽石やハイドロボールなど)
- 果樹用培養土を準備する(市販品で十分)
- 矮性品種の苗木を選ぶ(コンパクトに育つ品種がおすすめ)
- 植え付けを行う(地植えと同様の方法で)
- 支柱を立てて固定する(鉢用の支柱を使用)
- 適切な場所に設置する(日当たりが良く風通しの良い場所)
鉢植え栽培では、水やりが地植えよりも重要になります。
土の表面が乾いたらたっぷりと与えることが基本ですが、受け皿に水が溜まったままにすると根腐れの原因になるので注意が必要です。
特に夏場は朝夕の2回水やりが必要になることもあります。
鉢植えに適した品種を選ぶのもポイント。
- ひめこなつ:早生で小ぶり、鉢植えに最適
- ちよひめ:矮性品種でコンパクトに育つ
- 鉢植え白桃:鉢植え専用に改良された品種
- 花桃各種:実より花を楽しむなら管理が楽
私の知り合いのNさんは、マンションのベランダで鉢植えの桃を育てていらっしゃいます。
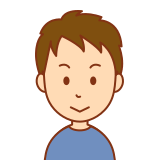
最初は本当に実がなるのか心配だったけど、3年目からちゃんと収穫できるようになった
と嬉しそうにお話しされていました。
鉢植えでも年に10〜20個程度の実を収穫することは十分可能です。
植え替えは2〜3年に一度行い、根詰まりを防ぐことも大切。植え替え時には古い根を整理して、一回り大きな鉢に植え替えるか、同じサイズの鉢で根を切り詰めて植え直します。
肥料は地植えよりも少し多めに、こまめに与えるのがコツ。液体肥料を月1回程度与えると、安定した成長が期待できますよ。
剪定の時期やコツ
桃の木の剪定は、美味しい実を収穫するためにも樹形を保つためにも欠かせない作業です。
適切な剪定を行うことで、病害虫の予防にもなり、風通しも良くなるので一石二鳥。
最初は難しく感じるかもしれませんが、基本を覚えれば意外と簡単なんですよ。
- 剪定時期を把握する(主剪定は12月〜2月、軽剪定は7月〜8月)
- 剪定道具を準備する(剪定鋏、のこぎり、消毒用アルコール)
- 樹形を決める(Y字型やハート型が一般的)
- 不要な枝を見極める(枯れ枝、病気の枝、交差枝など)
- 実際に剪定を行う(太い枝から細い枝へ順番に)
- 切り口に保護剤を塗る(病気の侵入を防ぐため)
- 剪定した枝の処分を行う(病害虫の温床にならないよう)
冬の主剪定では、まず全体の樹形を決めることから始めます。
桃の木は自然に上に向かって伸びる性質があるので、高さを抑えて横に広げるような剪定を心がけましょう。
剪定で取り除くべき枝には、以下のようなものがあります。
- 枯れ枝:完全に枯れた枝は根元から切り取る
- 病気の枝:縮葉病などにかかった枝は早めに除去
- 交差枝:他の枝と交差して日当たりを悪くする枝
- 内向枝:樹の内側に向かって伸びる枝
- 徒長枝:勢いよく上に向かって伸びる無駄な枝
- 下垂枝:下に垂れ下がって樹形を乱す枝
夏の軽剪定では、主に徒長枝の処理と風通しの改善が目的。
あまり強く切りすぎると翌年の花芽に影響するので、軽めに行うのがポイントです。
私が最初に剪定を習った時、ベテランの方から
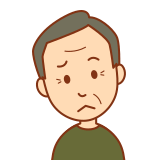
桃の木は花芽が前年の夏に作られるから、秋以降の強剪定は避けるように
と教わりました。この点を理解していると、剪定のタイミングで失敗することがなくなりますよ。
剪定のコツは、「迷ったら切らない」ということ。
経験を積むまでは、明らかに不要な枝だけを切るようにして、判断に迷う枝は翌年まで様子を見るのが安全です。
1本でも実がなる?
桃の木は基本的に自家結実性があるので、1本だけ植えても実をつけることができます。
これは桃を家庭で栽培する大きなメリットの一つ。
りんごや柿のように、受粉用の別品種を植える必要がないので、限られたスペースでも楽しめるんです。
ただし、品種によって自家結実性に差があるのも事実。
より確実に実をつけたい場合は、人工授粉を行うか、複数品種を植えることを検討してみてください。
自家結実性の高い品種をご紹介しますね。
- 日川白鳳:自家結実性が高く、家庭栽培に人気
- あかつき:安定して実がなり、初心者にもおすすめ
- 白鳳:古くからある品種で実つきが良い
- ひめこなつ:早生品種で鉢植えにも適している
一方、自家結実性が低く、他品種との受粉が必要な品種もあります。
- 川中島白桃:品質は良いが他品種の花粉が必要
- 浅間白桃:大玉で美味しいが自家結実性が低い
- 白桃:花粉が不完全で人工授粉が必要
人工授粉は思っているより簡単で、開花期(3月下旬〜4月上旬)に筆や綿棒で花粉を雌しべにつけるだけ。
私の近所のRさんは、
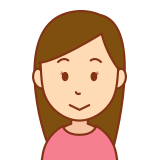
最初は面倒だと思ったけど、やってみると意外と楽しい作業
とおっしゃっていました。人工授粉した花に印をつけておくと、どの実が人工授粉で実ったのかがわかって興味深いそうです。
1本でも実はなりますが、人工授粉を行うことで実つきがより安定し、より多くの収穫が期待できます。
鉢植えの場合は、自然の昆虫が少ない環境になることもあるので、人工授粉はより効果的。
筆で軽く花をなでるだけの簡単な作業なので、ぜひ試してみてください。
寿命の目安
桃の木の寿命は、管理方法や環境によって大きく左右されますが、一般的には20〜30年程度とされています。
他の果樹と比べると比較的短命な部類に入りますが、その分成長が早く、植え付けから3年程度で実がなり始めるのが特徴です。
つまり、短期間で収穫の楽しみを味わえる果樹だということですね。
寿命に影響する主な要因をまとめてみました。
- 病害虫管理:適切な防除を行うことで寿命が延びる
- 剪定:正しい剪定で樹勢を保つことができる
- 土壌条件:水はけが良く肥沃な土壌で長生きする
- 気候条件:寒暖差が激しい地域では短命になりがち
- 品種:品種によって寿命に差がある
私の実家にある桃の木は、祖父が植えたもので既に25年以上経っていますが、まだ毎年たくさんの実をつけています。
適切な管理を続けていれば、30年以上楽しむことも十分可能だと思います。
寿命が近づくと、実のつきが悪くなったり、枝枯れが目立つようになったりします。
ただし、寿命が来る前に台風や病気で突然ダメになってしまうこともあるので、予備の苗木を育てておくのも一つの方法。
接ぎ木で品種を保存することもできるので、気に入った品種があれば技術を学んでおくのも良いでしょう。
また、桃の木は比較的短命な分、新しい品種に植え替えて楽しむという考え方もあります。
20年ほど楽しんだら、新しい品種にチャレンジしてみるのも面白いかもしれませんね。
長く楽しむためには、何よりも日頃の管理が大切。愛情を込めて育てた桃の木は、きっと長い間美味しい実を提供してくれますよ。
『桃の木は庭に植えてはいけない』のまとめ
ここまで桃の木を庭に植えることについて、デメリットから正しい育て方まで詳しく見てきました。
確かに「桃の木は庭に植えてはいけない」と言われる理由はいくつかありますが、そのほとんどが適切な知識と管理で解決できる問題だということがお分かりいただけたと思います。
改めて今回の内容をまとめると……
- 病害虫が多いのは事実だが、定期的な管理で十分対処可能
- 大きく育つが剪定や鉢植えでサイズコントロールできる
- 連作障害はあるが適切な植栽方法で回避できる
- 風水的な悪影響は迷信であり、むしろ縁起の良い木
- 動物被害は袋かけなどの対策で防げる
- 適切な品種選びと管理で1本でも十分収穫できる
桃の木は確かに手間がかかる果樹ですが、それ以上に得られる楽しみや満足感は大きなもの。
春の美しい花、夏の甘い実、そして魔除けとしての縁起の良さまで、多くの恩恵をもたらしてくれます。
私も実際に桃の木を育ててみて感じるのは、季節ごとの変化を楽しめることの素晴らしさ。
花が咲いた時の嬉しさ、実が膨らんでいく様子を見守る楽しさ、そして収穫の達成感は、他では味わえない特別な体験です。
もしあなたが桃の木を植えることを迷っているなら、まずは鉢植えから始めてみることをおすすめします。
管理方法を覚えて、桃の木の魅力を実感してから地植えに挑戦するのも良い方法ですよ。
■参照サイト:モモ – Wikipedia


コメント