山でアケビを見つけて「これ、庭に植えたら毎年実が楽しめるかも!」って思ったことありませんか?
私も以前、近所の人から「アケビって庭に植えちゃダメらしいよ」って聞いて、えっ?どうして?って不思議に思ったんです。
まず最初に要点だけをまとめると……
- アケビを庭に植えてはいけない理由は、旺盛な成長力と管理の手間にある
- 適切な場所選びと剪定を行えば、デメリットは十分カバーできる
- 複数株を植えれば、秋には甘い果実の収穫も楽しめる
「でも、山で普通に育ってるんだから大丈夫じゃないの?」って思いますよね。
実は、野生のアケビと庭で育てるアケビでは、管理の仕方がまったく違うんです。
この記事では、アケビを庭に植える際のリスクと、それを回避する具体的な方法を詳しく解説していきますね。
私自身も園芸が趣味で、つる性植物の扱いにはそれなりに経験があるので、実践的なアドバイスをお伝えできると思います。
アケビを庭に植えてはいけない5つの理由
アケビが「植えてはいけない」と言われる理由は、主に以下の5つに集約されます。
- つるが旺盛に伸びて他の植物や構造物に絡みつく
- 定期的な剪定管理を怠ると収拾がつかなくなる
- 害虫が発生しやすく、周囲の植物にも影響する
- 1本だけでは実がならない自家不和合性がある
- 海外では侵入種に指定されるほどの繁殖力がある
ただし、これらはすべて「管理をしっかり行えば防げる問題」なんです。
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
理由1:つるが伸びすぎて他の植物や構造物に絡みつく
アケビは落葉性のつる植物で、一年で数メートルも伸びる旺盛な成長力を持っています。
私の知り合いのKさんも、何気なくアケビを庭の隅に植えたところ、翌年には隣の木に巻き付いて、その木の日当たりを悪くしてしまったそうです。
アケビのつるは左巻き(Z巻き)に伸びて、近くにある樹木やフェンス、建物の外壁などに容赦なく絡みついていきます。
放置すると、絡みつかれた植物が日光を遮られて弱ったり、最悪の場合は枯れてしまうこともあるんです。
特に注意が必要なのは、以下のようなケースですね。
- 他の庭木の近くに植えた場合:つるが絡みついて成長を妨げる
- 建物の外壁近くに植えた場合:壁面に這い上がり、塗装を傷める可能性がある
- フェンス沿いに植えた場合:フェンスを覆い尽くし、隣家に侵入することも
ただし、この特性を逆手に取って、グリーンカーテンとして活用する方法もあります。
専用の棚やアーチを設置して、計画的につるを誘引すれば、むしろ夏の日差しを遮る便利な存在になるんですよ。
理由2:定期的な剪定管理を怠ると収拾がつかなくなる
アケビは毎年冬に強めの剪定を行わないと、枝が複雑に絡み合って手がつけられなくなります。
つるが伸びるスピードが速いため、一度サボってしまうと、翌年には枝が何重にも重なって、どこをどう切っていいのかわからない状態になってしまうんです。
剪定を怠った場合の具体的な問題点は以下の通り。
- 風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなる
- 古い枝と新しい枝が絡み合い、見た目が悪くなる
- 花芽が付きにくくなり、実の収穫量が減る
- 樹形が乱れて、庭全体の景観を損なう
適切な剪定時期は、落葉期の12月から2月頃です。
この時期に、混み合った古いつるや細くて弱い枝を根元から切り除き、太く元気なつるを選んで棚などに誘引し直します。
短く切り詰める強剪定が基本なので、「切りすぎかな?」と思うくらいでちょうどいいんですよ。
理由3:害虫が発生しやすく周囲の植物にも影響する
アケビには、アブラムシやカイガラムシといった害虫が付きやすいという特徴があります。
特にアケビコノハという大型のガの幼虫は、アケビの葉を食べて育つことで知られています。
この害虫が厄介なのは、成虫になると口吻が硬化して、ブドウやナシなどの果実に突き刺して果汁を吸うようになることなんです。
もし庭に果樹があると、アケビから害虫が移動して被害が広がる可能性があります。
また、ベニキジラミという小型の昆虫も、アケビの若い葉に寄生して虫癭(虫こぶ)を作ります。
- アブラムシ:新芽や若い葉の汁を吸い、すす病の原因にもなる
- カイガラムシ:枝や葉に付着して養分を吸い、樹勢を弱らせる
- アケビコノハ:幼虫が葉を食害し、成虫は果樹園の害虫になる
- ベニキジラミ:葉を変形させて虫癭を作る
風通しの良い場所に植えて、定期的に観察することが害虫予防の基本。
早期発見・早期対処を心がければ、被害は最小限に抑えられます。
理由4:1本だけでは実がならない自家不和合性がある
アケビには自家不和合性という性質があり、1本だけ植えても基本的に実はなりません。
「せっかく植えたのに実がならない!」という不満につながるのが、この理由なんです。
アケビは雌雄同株で、同じ株に雄花と雌花が咲きます。
でも、自分の株の花粉では受粉が成立しにくく、遺伝的に異なる個体の花粉が必要なんですね。
実を収穫したい場合は、以下の対策が必要になります。
- 異なる品種の株を2本以上植える(例:ミツバアケビとゴヨウアケビ)
- 近所にアケビがあれば、虫が花粉を運んで受粉することもある
- 確実に実をつけたいなら、開花期に人工授粉を行う
つまり、「1本植えただけでは意味がない」という声が出るのも、この自家不和合性が原因というわけ。
でも逆に言えば、複数株を植えて受粉対策をすれば、秋には甘い果実が楽しめるということです。
理由5:海外では侵入種に指定されるほどの繁殖力がある
実は、アケビは海外では「侵入種」「外来種」に指定されている地域があるんです。
19世紀頃にイギリスやドイツ、北アメリカへ観賞用・園芸用として持ち出されたアケビが野生化し、在来種の生息域を脅かしているんですよ。
特にアメリカ東海岸部では20以上の州で確認されており、現地の植物相に悪影響を与えているそうです。
これほどまでの繁殖力を持つ植物なので、日本の庭でも「一度植えたら手がつけられない」という事態になりかねません。
- つるが旺盛に伸びて広範囲に広がる
- 鳥や動物が種子を運ぶため、意図しない場所にも芽が出る
- 根が深く張るため、完全に除去するのが難しい
海外での事例は、アケビの繁殖力がいかに強力かを物語っています。
だからこそ、庭に植える際は、管理できる範囲に限定することが重要なんですね。
【結論】植える場所選びと管理をしっかりすれば問題なし!
ここまで読んで「やっぱりアケビは植えない方がいいのかな…」と思ったかもしれません。
でも実は、これらのデメリットは、適切な場所選びと定期的な管理で十分にカバーできるんです。
アケビを上手に育てるためのポイントをまとめると、こうなります。
- 専用の棚やアーチを設置して、つるを誘引する場所を限定する
- 他の庭木や建物から十分に距離を取って植える
- 毎年冬に強めの剪定を行い、つるの伸びをコントロールする
- 風通しの良い場所に植えて、害虫の発生を予防する
- 実を収穫したいなら、異なる品種を2本以上植える
私も以前、知り合いの庭でアケビの棚を見たことがありますが、きちんと管理されていれば、むしろ趣のある素敵な景観になるんですよ。
春には淡紫色の独特な花が咲き、秋には裂けた果実が甘い香りを放つ。
手間はかかりますが、それだけの価値はある植物だと思います。
「植えてはいけない」という噂に惑わされず、正しい知識を持って向き合えば、アケビは庭に彩りを添えてくれる存在になりますよ。
アケビは庭に植えてはいけない!を気にしない育て方
ここからは、具体的にアケビを育てる方法について解説していきます。
以下のポイントを押さえれば、「植えてはいけない」という噂を気にせず、安心してアケビを育てられますよ。
- 基本的な性質と種類を理解する
- 花言葉の誤解を解いておく
- 最適な植える場所を選ぶ(日当たり・風水面も考慮)
- 正しい植え方の手順を守る
- 自家不和合性を理解して複数株を植える
- 実がなるまでの期間を把握しておく
- 庭植えするメリットを最大限に活かす
- 寿命を知って長期的な計画を立てる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
基本情報(性質・種類・栽培難易度)
まずは、アケビの基本的な性質を理解しておくことが大切です。
アケビはアケビ科の落葉つる性木本で、日本の山野に自生している植物なんです。
北海道を除く本州(青森県三戸町以南)、四国、九州に分布していて、日本以外では朝鮮半島や中国にも見られます。
山の河畔や道端、雑木林など、やや日陰がちな場所で樹木に巻き付いて生育しているのをよく見かけますよね。
性質と特徴
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 分類 | アケビ科 落葉つる性木本 |
| 学名 | Akebia quinata |
| 樹勢 | 強い 成長は速い |
| つるの特徴 | 左巻き(Z巻き) 古くなると木質化 |
| 樹皮 | 暗灰褐色 細かくひび割れ |
| 葉 | 掌状複葉 冬でも残ることが多い |
| 花期 | 4月~5月 |
| 果期 | 9月~10月 |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
主な種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| アケビ (ゴヨウアケビ) |
小葉が5枚 最も一般的な種類 |
| ミツバアケビ | 小葉が3枚 葉の縁に鋸歯 |
| バナナアケビ | 果皮が淡い黄色 観賞価値が高い |
栽培難易度
| 評価 | 理由 |
|---|---|
| 初心者でも可 | 丈夫で病害虫に比較的強い 耐寒性・耐暑性が高い 土壌を選ばない |
| 注意点 | つるの管理が必須 定期的な剪定が必要 受粉対策が必要 |
アケビは基本的に丈夫な植物なので、初心者でも育てやすいのが特徴。
ただし、つる性植物特有の管理(剪定・誘引)を怠ると大変なことになるので、そこだけは注意が必要ですね。
葉は、短い柄を持つ楕円形の小葉が5枚集まってつく掌状複葉で、長い葉柄をつけてつる(茎)に互生します。
小葉は長さ3~6センチメートルの狭長楕円形で、先端が少しへこんでいるのが特徴的。
葉縁には鋸歯がなく全縁なので、触ってもトゲトゲしたりしません。
花言葉が「犠牲」のワケ
「アケビの花言葉は『犠牲』だから庭に植えるのは縁起が悪い」という話を聞いたことがあるかもしれません。
でも実は、これは完全な誤解なんです。
アケビの花言葉に「犠牲」や「献身」というものは存在せず、これは別の植物である「アセビ(馬酔木)」の花言葉なんですよ。
アケビとアセビは名前が似ているため、混同されてしまったんですね。
アケビの本当の花言葉
アケビの花言葉として知られているのは、以下のようなポジティブなものばかりです。
- 唯一の恋:雌雄異花でありながら同じ株に咲くことから
- 才能:つるが自在に伸びて成長する姿から
- 高潔:山野に自生する清楚な植物であることから
どれも素敵な意味ばかりで、「怖い」とか「縁起が悪い」というイメージはまったくありません。
アセビとの混同について
一方、アセビ(馬酔木)の花言葉は以下の通り。
- 犠牲:ギリシャ神話に由来する
- 献身:同じくギリシャ神話から
- 危険:有毒成分を持つことから
アケビとはまったく別の植物なので、花言葉も当然違うんですね。
私も以前、近所の方から「アケビは縁起が悪いって聞いたけど…」と相談されたことがありますが、この誤解を解いたらとても安心されていました。
ネット上の情報でも混同されているケースが多いので、正しい知識を持つことが大切です。
アケビには怖いイメージや縁起の悪さはまったくないので、安心して庭に植えてくださいね。
最適な植える場所(現実的な意味と風水面)
アケビを植える場所選びは、成功の鍵を握る最も重要なポイントです。
日当たり、風通し、そして何よりもつるを誘引できる施設があるかどうかが決め手になります。
現実的な観点と、風水的な観点の両方から、最適な場所を考えてみましょう。
現実的に最適な場所
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 日当たり | 日当たり~明るい半日陰 上部のつるには日が当たり 株元は日陰になる場所が理想 |
| 西日対策 | 真夏の強い西日は避ける 葉焼けの原因になる |
| 風通し | 良好な風通しが必須 病害虫予防になる |
| 土壌 | 水はけと水もちの良い土 粘土質は土壌改良が必要 |
| 誘引施設 | 棚・アーチ・フェンスなど つるを這わせる場所が必須 |
| 周辺との距離 | 他の庭木から1m以上離す 建物からも十分な距離を取る |
特に重要なのが、つるを誘引できる施設を用意することなんです。
専用の棚やアーチがあれば、つるの伸びる方向をコントロールできるので、管理がぐっと楽になります。
私の知り合いのMさんは、庭の西側にパーゴラを設置して、そこにアケビを這わせているそうです。
夏場は葉が茂って強い西日を遮ってくれるので、パーゴラの下が涼しくて快適な空間になっているとか。
アケビの旺盛な生育力を、グリーンカーテンとして上手に活用している好例ですね。
風水的に良い場所
| 方角 | 意味 |
|---|---|
| 東 | 成長・発展のエネルギー 若い木を植えるのに最適 |
| 南東 | 良縁・人間関係 つる性植物と相性が良い |
| 南 | 繁栄・名声 実をつける木に適している |
風水では、つる性植物は上へ上へと伸びていく性質から、「発展」や「良縁」の象徴とされています。
また、実をつける木は「成長・繁栄」を表すため、一般的に吉とされているんですよ。
ただし、風水的な要素よりも、実際の生育環境(日当たりや風通し)を優先することが重要。
迷信や縁起を気にしすぎて、日当たりの悪い場所に植えてしまっては本末転倒ですからね。
まずは植物が健康に育つ環境を整えて、風水はあくまで参考程度に考えるのがおすすめです。
植え方と注意点
それでは、実際にアケビを植える手順を詳しく解説していきます。
正しい手順で植え付けを行えば、その後の管理がぐっと楽になりますよ。
- 植え付け時期を選ぶ
最適な植え付け時期は、落葉期の11月から3月上旬です。特に秋の植え付けは、春植えよりも活着率が高いとされています。この時期は根が成長しやすく、春になる頃にはしっかりと根付いているんですね。 - 植え穴を掘る
つる性植物は根が広く張るため、植え穴は広めに掘ることが大切。直径50センチメートル、深さ40センチメートル程度を目安にしましょう。掘り上げた土には、腐葉土や堆肥をたっぷりと混ぜ込んで、水はけと水もちを改善します。粘土質の土壌の場合は、さらに赤玉土やパーライトを混ぜて、排水性を高めてくださいね。 - 支柱や誘引施設を設置する
これが最も重要なステップ。植え付けと同時に、つるを這わせるための支柱、棚、またはアーチを設置します。後から設置するのは大変なので、必ず植え付けの段階で用意しましょう。支柱は2メートル以上の高さがあるものを選び、しっかりと地面に固定してください。 - 苗木を植え付ける
根鉢を軽く崩して、根を広げながら植え穴に入れます。このとき、地表面よりもやや高めに植えるのがポイント。高植えにすることで、水はけが良くなり、根腐れを防げるんです。株間は1メートル以上あけると、風通しが良くなって管理が楽になります。 - 水をたっぷり与える
植え付け後は、たっぷりと水を与えます。根と土を密着させるために、水が引いてからもう一度水やりをする「二度水」を行うと、活着率がさらに高まります。 - つるを誘引する
植え付け直後から、つるを支柱や棚に軽く結び付けて誘引を始めます。麻ひもなどの柔らかい紐を使って、8の字結びにすると、つるを傷めずに固定できますよ。この初期の誘引が、その後の樹形を決める重要な作業なんです。
植え付け時の注意点として、複数株を植える場合は、必ず異なる品種を選ぶことが大切。
例えば、ミツバアケビとゴヨウアケビを一緒に植えると、相互に受粉して実がつきやすくなります。
また、枝が伸びすぎないように、年1回以上の剪定は必須。
定期的な管理を怠ると、あっという間につるが広がって手がつけられなくなるので、最初から計画的に管理する心構えが必要ですね。
1本で実がなる?「自家不和合性」について
「アケビを1本植えたけど、全然実がならない…」という悩みをよく聞きます。
実は、アケビには「自家不和合性」という性質があり、基本的に1本だけでは実がならないんです。
これはアケビを育てる上で、最も重要なポイントの一つと言えます。
自家不和合性とは
自家不和合性とは、同じ個体(または遺伝的に近い個体)の花粉では受粉が成立しにくい、または成立しない性質のこと。
アケビは雌雄同株なので、同じ株に雄花と雌花の両方が咲きます。
でも、自分の株の花粉では受粉が成立しないため、遺伝的に異なる個体の花粉が必要になるんですね。
これは植物が近親交配を避けて、遺伝的多様性を保つための仕組みなんです。
実をつけるための対策
アケビで確実に実を収穫したい場合は、以下の対策が必要です。
- 異なる品種の株を2本以上植える(ミツバアケビとゴヨウアケビなど)
- 近所にアケビがあれば、虫が花粉を運んで受粉することもある
- 開花期(4月~5月)に人工授粉を行う
- 受粉を助ける昆虫(小型のハナバチ類やハエ類)が訪れやすい環境を作る
人工授粉の方法は意外と簡単で、雄花の花粉を筆などで採取して、雌花の柱頭(先端部)に軽くつけるだけ。
雌花の柱頭には甘みを持った粘着性の液体が付いているので、花粉がそこに付着すれば受粉が成立します。
私の知り合いは、毎年4月になると綿棒を持って庭に出て、せっせと人工授粉をしているそうです。
ちょっと手間はかかりますが、秋に甘い実が収穫できると思えば、楽しい作業になりますよね。
受粉のメカニズム
アケビの受粉生態には、まだよくわかっていない点が多いんです。
雌雄異花で蜜も出さないため、どうやって虫を呼び寄せているのか謎なんですよね。
一つの仮説として、雌花が雄花に擬態して、雄花の花粉を目当てに飛来する小型のハナバチ類を騙して受粉を成功させているのではないか、と考えられています。
また、ハエ類が雌花の甘い粘着質を舐めに来る際に、体に付いた花粉で受粉していると考えられています。
自然界の仕組みって、本当に巧妙にできていますよね。
何年で実がなる?
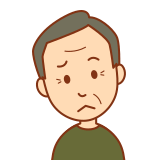
アケビを植えたら、いつ頃から実が収穫できるの?
という質問もよく受けます。
苗木を植え付けた場合、一般的には2~3年ほどで開花・結実が始まります。
ただし、これは苗の状態や管理状況、そして受粉状況によって前後するんですよ。
実がなるまでの期間
| 植え方 | 結実までの期間 |
|---|---|
| 2年生苗を購入 | 植え付けた翌年か 翌々年から結実開始 |
| 1年生苗を購入 | 2~3年後から 結実開始 |
| 種から育てる | 5年以上かかる ことが多い |
株が小さいうちは、花序に雌花を付けず雄花のみの花序となることも多いんです。
株が充実してくると、雌花が付くようになって、実がなり始めます。
最初の数年は実の数が少なくても、株が成長するにつれて収穫量は増えていくので、焦らずに見守ることが大切ですね。
早く実をつけるためのコツ
- 日当たりの良い場所に植える:光合成が盛んになり、株が充実する
- 適切な肥料を与える:春と秋に有機質肥料を施す
- 剪定を適切に行う:花芽を残しつつ、不要な枝を整理する
- 異なる品種を複数株植える:受粉がスムーズに進む
- 人工授粉を行う:確実に結実させられる
ちなみに、アケビの果実は9月から10月にかけて熟します。
成熟した果実の果皮は、心皮の合着線で縦に裂開して、内部の乳白色半透明で柔らかい果肉(胎座)と、黒い粒状の種子が露出するんです。
この胎座の部分が甘くて可食で、秋の味覚を代表する風味を楽しめます。
初めて自分で育てたアケビの実を食べたときの感動は、きっと忘れられない思い出になりますよ。
庭植えするメリット
ここまで「植えてはいけない理由」や「注意点」ばかり説明してきましたが、実はアケビを庭に植えるメリットもたくさんあるんです。
適切に管理すれば、アケビは庭に多くの楽しみをもたらしてくれる素晴らしい植物なんですよ。
主なメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 食用果実の収穫 | 秋に甘い果肉を収穫 果皮も料理に利用可 |
| グリーンカーテン | 夏の日差しを遮る 涼しい空間を作れる |
| 観賞価値 | 春の淡紫色の花 秋の裂開した果実 |
| 多用途利用 | 実・花・葉・茎・皮 つるまで利用可能 |
| 和風庭園に最適 | 日本の伝統的な 庭木として人気 |
| 目隠し効果 | フェンスに這わせて 自然な目隠しに |
| 丈夫で育てやすい | 耐寒性・耐暑性が強い 病害虫に比較的強い |
特に、グリーンカーテンとしての利用価値は高いです。
夏場、パーゴラや棚にアケビのつるを這わせておけば、密な葉が強い日差しを遮ってくれて、その下が涼しい憩いの空間になります。
しかも、秋には果実まで収穫できるんですから、一石二鳥どころか三鳥くらいの価値がありますよね。
果実の利用方法
アケビの果実は、果肉だけでなく果皮も食べられるんですよ。
- 果肉:そのまま食べると甘くて美味しい。種は食べずに出す
- 果皮:苦味があるが、油で炒めたり味噌炒めにすると絶品
- 若葉:山菜として天ぷらやおひたしに利用できる
- つる:工芸品(かご編みなど)に利用される
果皮の料理は、東北地方などでは郷土料理として親しまれています。
苦味が独特の風味となって、大人の味わいを楽しめるんです。
一つの植物でこれだけ多様な利用ができるのは、本当に魅力的ですよね。
景観としての価値
春になると、アケビは淡紫色の独特な形をした花を咲かせます。
花弁に見える部分は実は萼片で、雄花には6本の雄しべが、雌花には3~9本の雌しべが放射状につく姿は、なんとも言えない美しさがあります。
そして秋、裂開した果実が枝にぶら下がる様子は、まさに秋の風物詩。
和風庭園の趣を演出するには、これ以上ない植物だと思います。
寿命
「アケビって、どのくらい長生きするの?」という疑問も、よく聞かれます。
樹木としてのアケビの寿命は、一般的に20~40年程度とされています。
ただし、これは適切な管理を行った場合の目安で、実際にはもっと長く育てられる可能性もあるんです。
寿命を延ばすための管理
- 定期的な剪定:古い枝を更新して、株を若々しく保つ
- 適切な施肥:春と秋に有機質肥料を与えて、樹勢を維持する
- 病害虫対策:早期発見・早期対処で、株を弱らせない
- 誘引の管理:つるが過度に絡み合わないように整理する
アケビは、つる性植物の中でも比較的長寿な部類に入ります。
古くなった幹は木質化して、趣のある姿になっていくんですよ。
長年育てたアケビの古木には、それだけの歴史と風格が宿ります。
私も、山で見かける野生の古いアケビの株を見ると、何十年もこの場所で生き続けてきたんだなぁと感慨深くなりますね。
世代交代の考え方
ただし、20年、30年と育てていくうちに、株の勢いが弱まってくることもあります。
そんなときは、株元から出る新しいシュート(新梢)を育てて、世代交代を図るのも一つの方法。
古い幹を少しずつ切り戻しながら、若い枝に更新していけば、さらに長く楽しめます。
また、挿し木や取り木で株を増やして、予備の株を育てておくのもおすすめ。
お気に入りの株の「子孫」を残しておけば、万が一のときも安心ですよね。
長期的な視点で、アケビとの付き合いを楽しんでいくことが大切だと思います。
「アケビを庭に植えてはいけない」のまとめ
ここまで、アケビを庭に植える際の注意点と育て方について、詳しく解説してきました。
改めて、重要なポイントを振り返ってみましょう。
- アケビを庭に植えてはいけない理由は、旺盛な成長力と管理の手間にある
- つるが伸びすぎる問題は、専用の棚やアーチを設置して誘引すれば解決できる
- 定期的な剪定(12月~2月)を行えば、樹形をコントロールできる
- 害虫対策は、風通しの良い場所に植えて早期発見・早期対処が基本
- 自家不和合性があるため、実を収穫したいなら異なる品種を2本以上植える
- 花言葉の「犠牲」は誤解で、実際には「唯一の恋」「才能」「高潔」などポジティブな意味
- 適切な管理を行えば、グリーンカーテンや食用果実として庭に彩りを添えてくれる
アケビを庭に植えてはいけないという噂は、正しい知識と管理方法を知らないことから生まれたもの。
確かに、放置すれば手に負えなくなるリスクはあります。
でも、それは裏を返せば、それだけ生命力が強く、旺盛に成長する証拠でもあるんです。
その力を上手にコントロールして、グリーンカーテンや果実の収穫に活かせば、アケビは庭の素晴らしいパートナーになってくれますよ。
山で拾ってきたアケビを、庭に植えようか迷っているあなた。
この記事で紹介した管理方法をしっかり実践すれば、何も心配することはありません。
春には淡紫色の花を、秋には甘い果実を楽しめる、魅力的な庭づくりに挑戦してみてくださいね。
■参照サイト:アケビ – Wikipedia


コメント