お庭の中心に植える木を選ぶとき、迷いますよね。私も最初は「どの木が良いのかな?」とカタログを眺めては悩んでいました。
特に若い世代の方々は、忙しい日々の中でもお手入れしやすく、かつ季節の変化を感じられるシンボルツリーを求める傾向があるようです。
まずざっくりと結論をまとめると……
- 若い世代に好まれる要素は「手入れのしやすさ」と「季節感を楽しめる特性」
- 常緑樹と落葉樹はそれぞれに異なる魅力と適性を持っている
- あなたの生活リズムや庭の環境に合わせた選択が長く共に歩む秘訣
- 管理のしやすさと美しさのバランスを考慮することが大切
では、若い世代に人気のシンボルツリーの「ド定番10種類」と、その選び方を解説していきましょう。
常緑樹と落葉樹の違い(メリットやデメリット)など基本的なことも解説しますので、庭造り初心者の方も安心の内容ですよ。
若い世代に人気!シンボルツリーのド定番の10種類
以下の表は、若い世代に特に人気の高いシンボルツリー10種をまとめたものです。常緑樹と落葉樹、それぞれ5種類ずつをご紹介します。
| 種類 | 特徴 | 手入れ難易度 | 価格相場(2m前後) |
|---|---|---|---|
| シマトネリコ(常緑) | 細かな葉が涼しげで、洋風住宅に合う | ★☆☆(易しい) | 2.5万円~4万円 |
| ソヨゴ(常緑) | 風に揺れる葉が名前の由来、成長が遅い | ★☆☆(易しい) | 2万円~3万円 |
| ホンコンエンシス(常緑) | 花・実・紅葉と四季を通じて楽しめる | ★★☆(普通) | 2万円~2.5万円 |
| オリーブ(常緑) | 銀葉と食用の実が特徴、地中海風 | ★★☆(普通) | 3.5万円~6.5万円 |
| キンモクセイ(常緑) | 秋に芳香を放つオレンジ色の花が魅力 | ★☆☆(易しい) | 1.5万円~3万円 |
| アオダモ(落葉) | 自然樹形が美しく剪定の手間が少ない | ★☆☆(易しい) | 3万円~5万円 |
| ヤマボウシ(落葉) | 花・実・紅葉と三拍子そろった人気種 | ★★☆(普通) | 1.3万円~2.3万円 |
| エゴノキ(落葉) | 和洋どちらの庭にも合う、花が美しい | ★★☆(普通) | 1.9万円~4.4万円 |
| ジューンベリー(落葉) | 花・食べられる実・紅葉を楽しめる | ★☆☆(易しい) | 1.2万円~3万円 |
| カツラ(落葉) | ハート形の葉が特徴、自然樹形が整う | ★★☆(普通) | 2.3万円前後 |
これらの木々は、それぞれに個性があり、お庭の雰囲気や管理のしやすさなど、あなたの優先事項によって選ぶとよいでしょう。次からは、それぞれの木の特徴について詳しくご紹介していきますね。
常緑樹のシンボルツリーの定番5種類の特徴
庭に一年中緑を保ちたいなら、常緑樹は外せない選択肢です。私も自宅の庭に常緑樹を植えていますが、冬でも青々とした葉が見られるのは心が安らぎますよね。
常緑樹は葉が一年中残るため、プライバシーの確保にも役立ちます。ここでは、特に人気の高い5種類の常緑樹について詳しくご紹介します。
シマトネリコ – 軽やかな印象が魅力

シマトネリコは、涼しげな葉が揺れる姿が本当に美しい木です。私の友人の家にも植えられていますが、風が吹くたびに葉がゆらゆらと踊るように揺れて、見ているだけで心が和みます。
- 繊細な葉が風に揺れる姿が特徴的で、洋風やモダンな住宅との相性抜群
- 半常緑性で北国では葉が落ちることもあるが、関東以西なら常緑性を保つ
- 成長が早く、年間20cm程度伸びるため定期的な剪定が必要
- 樹高は3m程度に抑えるのが一般的で、主幹を切って高さ制限するのがポイント
シマトネリコは耐暑性に優れていますが、耐寒性はそれほど高くありません。-5℃程度まで耐えますが、それ以下になると葉が傷むことも。水やりは植え付け2年目までは注意が必要ですが、それ以降はほとんど不要です。病害虫にも強く、初心者の方でも育てやすい木なのが嬉しいポイント。
ソヨゴ – 風にそよぐ葉が名前の由来
ソヨゴは日本の在来種で、風に葉が揺れる様子から名付けられました。私はこの木の濃い緑色の葉と赤い実のコントラストが大好きです。
- 濃緑で光沢のある葉が風に揺れると「そよそよ」と音を立てる
- 雌株は秋から冬に赤い実をつけ、鳥が集まる自然豊かな庭に
- 成長が極めて遅く、年間20cm程度しか伸びないため管理が楽
- 日陰にも強いため、日当たりの悪い場所のシンボルツリーとしても活躍
ソヨゴの剪定は2年に1回程度で十分です。ただし強い剪定は禁物で、徒長枝のみを切除するのがコツです。耐寒性・耐暑性ともに強く、北海道南部から沖縄まで幅広い地域で育てることができます。カイガラムシやすす病には稀に注意が必要ですが、総じて病害虫に強い木です。
ホンコンエンシス – 四季を通じて楽しめる常緑ヤマボウシ
ホンコンエンシスは常緑ヤマボウシとも呼ばれ、四季折々の表情を楽しめる木です。我が家でも玄関前に植えていますが、季節ごとに違う顔を見せてくれます。
- 6~7月に月明かりのような白い花が密集して咲く姿は圧巻
- 光沢のある葉に黄緑のグラデーションが入り、見る角度によって表情が変わる
- 年間30cm程度の成長で3~5年後に急速に育つ傾向あり
- 寒冷地では半常緑性になり冬季に葉を落とすことも
水はけの良い肥沃な土壌を好み、植え付け時は腐葉土や赤玉土を混ぜるとよいでしょう。自然樹形を維持しやすく、徒長枝の切り戻しも容易なので、剪定の初心者でも扱いやすい木です。ただし浅根性のため強風時は支柱が必要なことに注意しましょう。
オリーブ – 地中海の雰囲気を庭に
オリーブの銀緑色の葉は、風に揺れるとキラキラと光を反射して美しいんです。私も数年前から鉢植えのオリーブを育てていますが、その姿に癒されています。
- 表が濃緑色、裏が銀白色の葉が風に揺れると際立つコントラストが魅力
- 品種によって開帳型(横に広がる)と直立型(上に伸びる)があり庭に合わせて選べる
- 自然放置すると10m近くまで成長するが、剪定で2~3mに抑制可能
- 地中海風やナチュラルモダンな庭造りにぴったり
オリーブは排水性の良いアルカリ性土壌を好みます。日当たりを好むので、半日以上日光が当たる場所に植えるのがおすすめです。剪定は枝の混み合いを防ぐため強めに行うのがコツ。根が浅いので幼木時は支柱が必要です。耐寒性は中程度で、霜には注意が必要です。
キンモクセイ – 秋の香りの代表選手
キンモクセイといえば、秋に漂う甘い香り。私も子どもの頃から「この香りが漂うと秋だなぁ」と感じていました。庭に植えれば、毎年その季節感を楽しめます。
- 9~10月に開花するオレンジ色の花から漂う甘く強い香りが特徴
- 自然状態では5~10mまで成長するが、剪定で2~3mに管理可能
- 耐暑性が強く、東北南部以南で育成可能
- 病害虫に強く初心者でも育てやすい
手入れのポイントは、花後すぐの剪定と定期的な高さ管理です。剪定を怠ると樹高が過度に伸びてしまうので、スペースに応じた管理計画を立てておくことが大切です。水やりは地植えなら植え付け半年後からほぼ不要で、肥料は年に2回(2月・9月)与えるのがおすすめ。和風から洋風まで幅広い庭のスタイルに合う万能な木です。
落葉樹のシンボルツリーの定番5種類の特徴
四季の移り変わりを感じたいなら、落葉樹は素晴らしい選択です。私も自宅の庭に落葉樹を植えていますが、春の新緑、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の枝ぶりと、一年を通じて様々な表情を見せてくれるのが魅力的。
ここでは、人気の高い5種類の落葉樹について詳しくご紹介します。
アオダモ – 自然樹形の美しさが魅力

アオダモは日本原産の木で、何もしなくても美しい樹形になる不思議な木です。私の母が住む実家の庭にもアオダモがあり、四季折々の姿に心が和みます。
- 自然のままでも美しい樹形が特徴で、剪定の頻度が少なくて済む
- 春の白い花、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の枝模様と四季を通じて楽しめる
- 成長速度が遅く(年間約30cm)、管理が容易
- 株立ち仕立ての苗木が雑木風の自然な庭に最適
水やりは成木になれば雨水だけで十分ですが、夏の乾燥時には散水するとよいでしょう。剪定は落葉期に不要枝を切除し、自然な樹形を維持するのがポイントです。肥料は冬に寒肥を1回程度与えれば十分で、成木では必須ではありません。褐斑病やうどん粉病には注意が必要ですが、葉の除去で対応できます。
ヤマボウシ – 花・実・紅葉の三拍子そろった人気種
ヤマボウシは一年を通じて様々な表情を見せてくれる木です。私も友人の庭で見かけるたびに「こんなに美しい木があるんだなぁ」と感動します。
- 6月頃に白い手裏剣状の花が咲き、秋には甘みのある赤い実がなる
- 光沢のある葉は秋に美しく紅葉し、半日陰でも映える
- 樹高は自然では10~15mになるが、剪定で3m程度に管理可能
- 水やりがほとんど不要で管理が楽
ヤマボウシの剪定は11月~2月に行いますが、花芽を残すよう注意することがコツです。高さ抑制には若木時の「芯止め」(主幹を3m程度で切断)が効果的です。日当たりが悪いと花付きや紅葉の美しさが損なわれるため、半日陰~日向が最適な環境です。和風でも洋風でも調和する点も魅力で、ナチュラルテイストの庭に特におすすめです。
エゴノキ – 自然樹形を活かせる日本在来種
エゴノキは日本の在来種で、人の手をあまり加えなくても美しい姿を保つ木です。私の近所の公園にもエゴノキがあり、初夏の白い花が風に舞う様子は幻想的です。
- 細い幹から四方に枝を伸ばす自然樹形が美しい
- 春の柔らかい緑、夏の濃い緑と季節による葉色の変化を楽しめる
- 5~6月に白やピンクの花を咲かせる(品種「ピンクチャイム」は特に人気)
- 和風・洋風どちらの庭にも馴染む汎用性の高さ
剪定は年2回(1~2月の樹形調整と5~6月の軽剪定)が推奨されますが、比較的病害虫に強く、剪定頻度も少なくて済むため、手入れは容易です。ただし、樹高が高くなるため定期的な芯止め剪定が必要な場合もあります。実の皮にはエゴサポニンという毒性成分を含むため、小さな子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。
ジューンベリー – 食べられる実も魅力的
ジューンベリーは花、実、紅葉と三拍子そろった魅力的な木です。私も小さな鉢植えのジューンベリーを育てていますが、春の花も秋の紅葉も美しいんですよ。
- 春には白い小花が鈴なりに咲き、初夏には食べられる赤黒い甘い実がなる
- 秋には美しい紅葉が楽しめる四季折々の変化が魅力
- 樹高は自然では3~5m程度だが、矮性品種では1.5~2m程度に
- 耐寒性・耐暑性に優れ、全国で栽培可能
ジューンベリーの剪定は「果実収穫後の枝透かし」と「落葉期の樹形調整」が基本で、徒長枝を基部から切除する程度で十分です。病害虫への抵抗力が強く、無農薬栽培も可能なため、エコ志向の方にもおすすめ。水やりは地植えなら降雨のみで十分で、肥料も年に1回の寒肥だけでOKという、まさに低管理の優等生です。
カツラ – ハート形の葉が愛らしい
カツラは日本原産の落葉高木で、ハート形の葉が特徴的な木です。私の祖父の家の庭にあったカツラの木の下で遊んだ思い出があります。
- 心材は褐色、辺材は黄白色で、色の濃淡によりヒカツラとアオカツラに区別される
- 柔らかな樹形が雑木林の雰囲気を醸し出す
- 最終樹高は15~20mに達するが、剪定で3~5m程度に抑制可能
- 湿潤な土壌を好むため、水はけの良い場所での植栽が理想的
カツラの剪定では、高さ抑制のために上枝から順に分岐点で切断するのがポイントです。太すぎる枝を優先的に剪除して樹勢を調整し、同じ位置での連続剪定はコブ形成の原因になるので避けましょう。適切な管理下では年間30~50cm程度の成長が見込まれます。自然風の庭園や和風庭園に植えると、柔らかな印象を与えてくれます。
常緑樹と落葉樹の違いやメリット/デメリット
お庭のシンボルツリーを選ぶとき、常緑樹にするか落葉樹にするか迷いますよね。私も庭づくりを始めたときは「年中緑があるほうがいいのかな?」「でも紅葉も楽しみたいな…」と考えていました。
実は両者には明確な特徴があって、どちらを選ぶかで庭の雰囲気がガラリと変わるんです。それぞれの特性を知れば、あなたの理想の庭づくりにぴったりの木が見つかるはず!
常緑樹と落葉樹の基本的な違い
常緑樹と落葉樹、名前は知っていても具体的に何が違うのか、意外と知らないことも多いですよね。私も最初は「常緑樹は冬も葉っぱがあるやつでしょ?」くらいの理解でした。でもそれだけじゃないんです。
- 常緑樹:1年を通して葉を保持し、古い葉と新しい葉が少しずつ入れ替わる
- 落葉樹:季節ごとに一斉に葉を落とし、春に新しい葉をつける
- 常緑樹の葉:厚くて光沢があり、水分保持能力が高い
- 落葉樹の葉:薄く、秋に紅葉して落ちる特性がある
常緑樹は一見すると「葉が落ちない」と思われがちですが、実は少しずつ古い葉を落として新しい葉に入れ替えているんです。だから一年中緑を保っているように見えるんですね。
対して落葉樹は、冬の寒さに耐えるため葉を落とすという生存戦略を取っています。これが四季の変化を感じさせてくれる理由。
自然の知恵がつまった葉のライフサイクル。それぞれの樹木が持つ特性を知ると、庭づくりの楽しさも倍増しますよ。
常緑樹のメリット・デメリット
常緑樹を選ぶとどんな庭になるのか、具体的なイメージを持つことが大切です。私の友人は「プライバシーを守りたい」という理由で常緑樹を選びましたが、その選択は大正解だったようです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 一年中緑があり安定した景観を保てる | 葉が厚く重々しい印象を与えることがある |
| 目隠し効果が年間を通して持続する | 下草の生育を妨げやすい |
| 落ち葉の量が少なく掃除の手間が少ない | 移植時に葉が落ちるリスクがある |
| 四季を通して日差しを遮ってくれる | 寒さに弱い種類が多い |
プライバシー保護が重要なお宅では、常緑樹が大活躍します。特に道路に面したお庭や隣家との境界には、シマトネリコやソヨゴなどが人気なんですよ。
ただし常緑樹は「重たい印象」になりがちなので、庭全体のバランスを考えて配置するのがポイント。私の庭では、常緑樹と落葉樹をバランスよく配置することで、年中緑のある安定感と季節の移り変わりの両方を楽しんでいます。
「掃除が楽」というのも嬉しいポイント。落ち葉が一気に降り積もることがないので、秋の大掃除の手間が省けるんです。忙しい方には特におすすめですね。
落葉樹のメリット・デメリット
落葉樹の魅力は何と言っても「季節感」。私の庭のヤマボウシは、春の花、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の枝ぶりと、一年を通して表情を変えてくれるんです。本当に見ていて飽きません!
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 四季の変化を存分に楽しめる | 冬季は目隠し効果がなくなる |
| 夏は日陰、冬は日光を取り入れられる | 落ち葉の処理に手間がかかる |
| 成長が比較的早い種類が多い | 剪定は休眠期に限られる |
| 寒冷地に適応した種類が多い | 季節ごとの景観変化を計画する必要がある |
落葉樹の最大の特徴は、季節によって全く違う表情を見せてくれること。特に紅葉する種類は秋の庭を華やかに彩ってくれます。アオダモやエゴノキなどは自然な雰囲気が素敵で、和風の庭にもよく合います。
また落葉樹は夏と冬で日差しの調節をしてくれるという優れた特性も。夏は涼しい木陰を作り、冬は葉を落として太陽の光を取り入れてくれるんです。これって自然の恵みですよね。
ただし「落ち葉の掃除」は避けられない宿命。私は「落ち葉集めは秋の風物詩」と前向きに捉えていますが、忙しい方や高齢の方には少し負担かもしれません。その場合は落葉の少ない種類を選ぶか、業者さんにお願いするのも一つの手段です。
庭のタイプ別おすすめの選び方
あなたはどんな庭を作りたいですか?目的や好みによって、常緑樹と落葉樹の選び方も変わってきます。私の経験から、いくつかのパターン別におすすめをご紹介します。
- プライバシー重視の庭:常緑樹(シマトネリコ、ソヨゴなど)
- 四季を楽しむ庭:落葉樹(ヤマボウシ、ジューンベリーなど)
- 手入れを簡単にしたい庭:管理の楽な常緑樹(オリーブ、ホンコンエンシスなど)
- 和風の庭:キンモクセイやエゴノキ
- 洋風の庭:オリーブやシマトネリコ
「両方の良さを取り入れたい!」という欲張りな方(私もそうでした)には、常緑樹と落葉樹をミックスする方法がおすすめ。例えば、境界線には常緑樹を植えてプライバシーを確保しつつ、庭の中心には落葉樹を植えて季節感を楽しむという組み合わせ。
また庭の広さも考慮すべき重要なポイント。狭いスペースなら成長がゆっくりで管理しやすいソヨゴなどがおすすめですし、広い庭ならヤマボウシのように枝を広げる樹種が映えます。
私の庭では、南側の日当たりの良い場所に落葉樹のヤマボウシを、西日が強く当たる場所には常緑樹のソヨゴを植えています。これで夏は涼しく、冬は日当たりよく、年中プライバシーも守られているという理想的な環境になりました。
シンボルツリーの選び方のまとめ
シンボルツリー選びには様々な視点があることがお分かりいただけたかと思います。最後に、シンボルツリー選びで押さえておきたいポイントをおさらいしておきましょう。
庭づくりは長い時間をかけて育てていくもの。だからこそ、あなたのライフスタイルや好みに合ったシンボルツリーを選ぶことが、後々の満足度を大きく左右します。
- 若い世代には管理のしやすさや季節の変化を楽しめる樹種が人気
- 常緑樹は年間を通して安定した景観とプライバシー保護に優れる
- 落葉樹は四季折々の表情が楽しめ、夏は日陰・冬は日光を取り入れる特性がある
- 庭の目的や広さに合わせて、最適な樹種を選ぶことが大切
私自身、シンボルツリーに囲まれた庭での生活は、想像以上に心が豊かになります。朝、カーテンを開けて見える木々の様子に季節を感じ、ホッとする瞬間が日々の小さな幸せになっています。
シンボルツリーの選び方に正解はありません。あなたの生活スタイルや好みを大切に、長く付き合っていける樹木を見つけてくださいね。きっと素敵な庭づくりができるはずです!

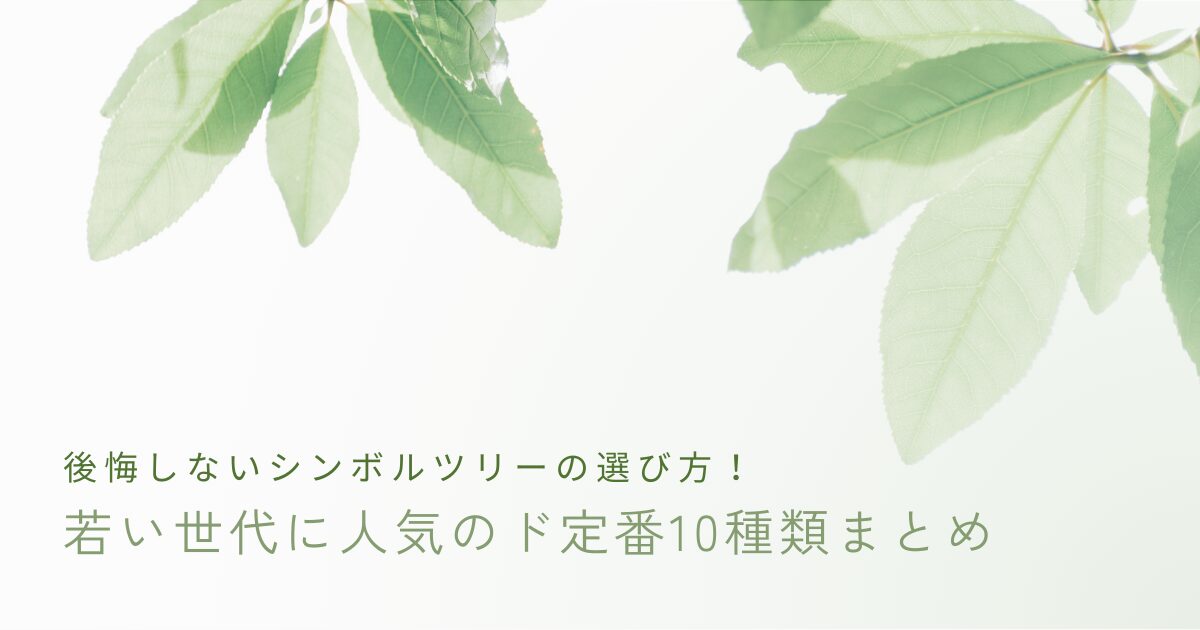
コメント